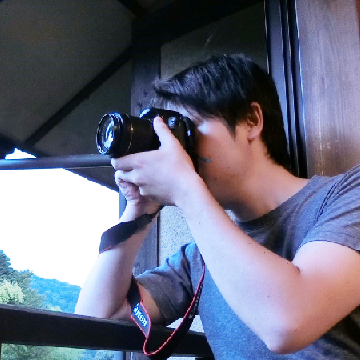世間では「男性も育児休暇を!」という風潮ですが、実際にパパも育児休暇を取得すべきなのでしょうか?
今回は、パパが育児休暇を取得するメリット・デメリットからその必要性を考えてみました。ぜひ、我が家を振り返りながら、取得すべき派・すべきでない派か考えてみてください。
<記事の内容はこんな感じ>
1.パパの育児休暇取得率はわずか5%ほど
2.パパが育児休暇を取得するメリット
3.パパが育児休暇を取得するデメリット
4.まとめ
1. パパの育児休暇取得率はわずか5%ほど
積水ハウス株式会社の発表した「イクメン白書 2019」によると、「育休を取得したい」と答えたパパは60.5%となっており、おおむねパパたちは育児休暇に対して積極的な印象です。
しかし、内閣府の「共同参画 2018年6月号」では、2017年時点において、育児休暇取得率は、ママが83.2%であるのに対して、パパはわずか5.14%。まだまだ浸透していないのが現状です。
2. パパが育児休暇を取得するメリット
パパの育児休暇取得率が十分でない理由のひとつとして、そのメリットが浸透していないことが挙げられます。では、育児休暇を取得することでどのようなメリットがあるのでしょうか。
<ママの育児負担を軽減できる>
出産によってママの身体は、文字通り「ボロボロ」な状態になり、回復するための期間が必要です。しかし、育児に「待った」はなく、数日後から赤ちゃんのお世話が始まります。
そんな時、パパが育児休暇を取得すれば、オムツ替えやお風呂など、赤ちゃんのお世話の大半をパパに任せることができ、粉ミルクを活用すれば、ママは身体を休めることに集中できます。
さらに、パパが育児に参加することで、赤ちゃんのお世話をする大変さが身にしみて分かりますから、仕事に復帰した後も育児に奮闘するママへの理解も深まるはずです。
<育児に参加しやすくなる>
育児休暇を取得し、一時的でもパパが主体で育児をしていれば、おむつ替えやお風呂、ミルクなど育児に必要なスキルは自然と身につきます。パパだって必要に迫られればできるのです。
そして、一度自信がつけば、育児に参加するハードルはグッと下がります。
例えば、ママが体調を崩したとしても、パパがいれば子どものことは安心です。やり方が分かっているのですから、育児休暇後もパパから積極的に育児参加してくれることでしょう。
<子どもと関わる時間が増える>
子どもと関われる時間はそう長くはありません。長くとも大学入学までの18年間。まして、密接に関われるのは、生まれてから小学校入学までの6年間くらいと、時間は限られています。
児童心理学において、親子関係が形成されるのは生後6ヶ月までとされており、その期間は本当に重要。子どもが「パパ見知り(苦手)」になるのは、親子関係ができていないためです。
その点、パパが育児休暇を取得すれば、子どもと関わる時間をしっかり確保できるので、子どもとの親子関係を形成できます。子どもが懐けば、パパも親としての自覚が持ちやすいはずです。
3. パパが育児休暇を取得するデメリット
ご紹介したメリットですが、すでに理解しているパパも多いと思います。それでも、パパの育児休暇取得率がわずか1桁台と十分でないのは、それを妨げる何らかの障害があるからでしょう。
<一時的にでも収入が減少する>
男女共同参画社会が提唱されてからすでに20年が経過しました。でも、世間を見渡すと、パパが仕事で家計を支えて、ママは家事や育児で支える、という家庭はまだまだ多いです。
その為、もしパパが育児休暇を取得すると、家庭の収入が減少してしまいます。もちろん、「育児休業給付金」を取得すればある程度補填はできますが、通常の給与の6割程度です。
子育てにはとにかくお金がかかります。オムツ代やミルク代を始め、子どもはすぐに大きくなるので衣装代も。「家計が厳しくなるから…」と育児休暇を断念してしまうパパは多いのです。
<会社での立場が悪くなる可能性がある>
正確なデータはないのですが、男性が育児休暇を取得するのに否定的な会社は少なくありません。会社としても重要な戦力が何ヶ月もいなくなるのですから、応援しづらいのでしょう。
そして、会社によっては無理に育児休暇を取得すると、復帰後に不本意な異動をさせられたり、出世が難しくなるという話も耳にします。これでは育児休暇が取得しづらいのも納得です。
4. まとめ
今回、パパが育児休暇をすることで考えられるメリット・デメリットをまとめてみました。
その家庭ごとに環境は様々なので、一概に「これが正解だ!」とは決して言えません。しかし、育児休暇は子どもとの時間を作れる大切な機会なので、少しでも取得してもらいたいもの。
まずは夫婦でよく話し合い、家庭にとって、子どもにとって何が最適なのか考えてみてください。
 お気に入り
お気に入り